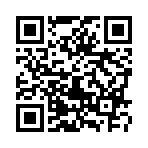2012年10月08日
新しい料理法の誕生・・・

先日ブログで紹介した「モレキュラー ガストロノミー」、いわゆる「分子料理学」について、もっと詳しく教えてくれとの
メッセージをたくさん頂戴しました。
この本の著者のエルヴェ ティスが発表したのは、これまで料理人の経験に頼りがちだった料理の調理法を
物理学や化学を駆使して解消しょうとする学問の分野にまで昇華したのですね。
彼は「あらゆる料理は、物理化学の式で表せる」とこの本の中で言ってます。
彼は料理とは、次の食材の4状態と分子活動の4状態の組み合わせにより表現できると考えたのですね。
(食材の状態)
G (ガス)・・・・・・気体
W (水)・・・・・・・液体
O (オイル)・・・・油脂
S (ソリッド)・・・・固体
(分子活動の状態)
/・・・・・・・・・・・・・分散
+・・・・・・・・・・・・併存
&・・・・・・・・・・・・包含 結合
$・・・・・・・・・・・・重層
例えば、泡立てる前の生クリームは「水の中に油脂が散らばっている」状態。
式だと、O/W (油脂・分散・水分)
「生クリームを泡立てる」と言う調理法は油脂に空気を含ませるから、油脂(O)に空気(G)を加え(+)、その
空気を含んだ油脂が水の中に散らばっている(/)状態。
すなわち式にすると・・・
(O+G)/W (油脂・加える・空気・分散・水分)
こうした記号を用いて実際のレシピを数式にしてメニューを分解したのですね。
例えば、油脂を表すOのところを、油脂分を含むチーズに置き換えたら、理論的にはホイップチーズが出来るはずでありますね。
ただ、これだけで料理に仕上げることが出来るか?
この問題を解決したのが、フランスの超有名シェフのピエール・ガニエールですね。
現在ではフェラン・アドリア、ダニ・ガルシア、サンセバスチャンのアルサックと続々誕生してますね。
この「分子料理学」って実に面白い!
但し、やたら専門用語やフランス語が出て、まだまだ・・・・また勉強してわかりやすくお教えしますね。
Posted by pepe at 07:31│Comments(0)